
通勤や通学で毎日利用している「ママチャリ」
ギア変速の使い方を少し知っているだけで、走りが快適になる可能性があります。
記事を読み終わる頃には普段気にもせず使用していた変速機能について少し詳しくなれます!!
購入時は変速無しと6段変速では「6段の方が快適そう!!」と思って購入したはずです。
スポーツタイプの自転車なら「6段よりは8段の方が速い!!」
それなら、俺のは後ろに10段、前に2段だから20段変速だぞ~!!
そしていつもの・・・20段変速で隣のヤツに差を付けろ!!
昭和のジュニアスポーツのキャッチの呪縛にいまだに縛られている自分に気付くことなるのです。
時は令和なのに・・・
変速機はペダルの力を効率よく速度に変換することです。
足の力を自転車の進む力に変えることです。(同じですね)
効率よいペダリングとは、自分の持っている力を効率よく回転運動にかえることです。
重すぎてペダルが回せない・・・(スタート時にもたつく)
逆に、ペダルの回転は速いのに速度がでない・・・(シャカシャカ回しているのに速度が出ていない)
このような時は「ギアの選択が適正でない」のかも知れません。
ギアを重くすれば速くなる訳でもなく、軽くすれば遅くなる訳でもありません。
重要なのは自分の持っている力を効率よくペダルの回転運動に変換し、その回転運動を持続させることです。
重いギアでペダルを回し、速度が出たら休む・・・
速度が落ちてきたらペダルを回す・・・
このようなペダリングは一見楽に感じます。しかし実際は効率が悪く疲れやすいです。
急な動作をなるべく減らし、一定の速度で走ると想像以上に楽に走ることができます。
これは変速ギアの少ない「ママチャリ」だけでなく「ロードバイク」でも基本は同じです。
ギア数(段数)が多ければ「速く」なる訳ではなく、足の力を効率よく回転運動に変換するいわゆる「ペダリング」の選択肢が増えると考えてください。
ギア数(段数)が多ければ自分の持っている力を有効に使える「パワーバンド」を利用できます。
結果、トータルで見た時、「楽に、速く」移動できることになるのです。
【結論】変速機はこまめに操作すること!!
今回の結論はずばり!!
走行時に「ガチャガチャ操作する」これだけのことです。
以上となります。
こんなに簡単なのになぜわざわざ変速機の記事を作成したのか?
「ついてるのに使わなきゃ損!!」だからです。
せっかく購入時に変速付きを選んだのに、それを忘れたかのように使用していない方も見かけます。
これはもしや・・・変速機の使いかたを知らないのでは?
止まる前には「軽いギア」にしておく!!
これだけでも明らかに効果があります。
しかし、分からないのなら「とにかく動かそう!!」こういう力技?も必要です。
実際に操作して「身体で感じるのもあり」ではないでしょうか?
- 変速機はこまめに操作する!!
- とにかく動かしてみよう!!
身体にやさしいギアの選択を!!
ギアの選択と言っても極端に言えば「軽い」か「重い」だけです。
適正なギアを選択していれば、安定した走行をしやすくなります。
2つのパターンを説明します。
まったりペースで ふらつくパターン
妙にふらついている「ママチャリ」を見かけることがあります。
走行スピードは歩く速度より少し早いくらいです。
速度が出ていないからふらつくのも当然なのです。
よく見てみるとギアがトップ側(小さい方)から3枚目位で、ギアの選択が「重すぎる」のが原因だったりします。
- これではペダルが重すぎて回せない
- 回せないから速度が落ちる
- 速度が落ちるからふらつく
速度が落ちる前にペダルが回しやすいロー側(大きい方)へ、「ガチャッ」と変速しておいた方がいいですね。
ペダルが重くて回せなくなってふらついてしまい、「最後はどうするのか?」と思ったら「飛び降りる?」のは年配の方に多い降り方です。見ていて危なかしいですね。
とにかく回せで 忙しい(シャカシャカ)パターン
これはスポーツ系に多いパターンです。「ロードバイク」でも初心者?なんだろうな~という方に見られます。
速度はそれ程出ていないのに、ペダルだけが高速回転!!
心拍数を上げるためのエクササイズでもしているのか分かりません。
「弱虫ペダル」坂道君の高速ケイデンスの影響だったのか~?最近視聴して勝手に納得している次第です。
ケイデンスとはクランク回転数のことです。「ロードバイク」で70~100/分が目安です。
ゆったり走る「ママチャリ」なら50~70/分?
60/分回転でも継続するのは大変です。
足の回転が付いていいかず、支点であるサドルの上でお尻が
「ピョンピョン」しているのは足の回転が間に合っていない証拠です。
これはギアの選択が軽すぎるのでトップ側へ1~2枚変速することをおすすめします。
大きく分けてこの2つのパターンになります。
重いか軽いかしかないのですが・・・
次は基本的なギアの選択方法を紹介します。
ギアの選択の表現を「段」か「枚」?弱虫ペダルを視聴後あたまを悩ませるのでした。
ご了承くださいませ。最近は「枚」表現がマストか?
ギア選択の自由!!なんだが・・・
「職業選択の自由」と同じように「ギアの選択も自由」です。(バブリーなフレーズ、分かる方は40代以降?)
選択の自由があるのになぜ使用しない?いや変えられないのか?
それは「恒常性維持機能」と言うものがあって、人間なかなか変えられないものです。
よく言われる「ホメオスタシス」という・・・この辺にしておきます。
すでに6段のギアが「ママチャリ」には付いている。
なのになかなか変えられない理由かも?
- 重いギアで「ウンウン」こぐのに慣れている人はそれがあたり前になります。
- 逆に軽いギアで「クルクル」回すのに慣れている人はそうなります。
使い方が分からないのが正解ではないでしょうか?
- 何となく今のギアで走っているから、普段の走行時には変速をせずに使っている
- 使ってはいるが速く走りたい・・・トップギアへ。坂道だから・・・ローギアへ
ほとんど固定派と「トップ」と「ロー」の極端派に分かれたりして・・・
子供の変速パターンを参考にしてます。
【変速機】使い方の基本 6段編

↑写真はロードバイクの8段です
少し内容がそれたので、元に戻します。
- トップから4枚目に入れてこぎだす
- クランクの回転数が上がってきたらトップ側へ1枚分変速
- 更にスピードが上がりクランクの回転数が上がったらトップ側へもう1枚
- クランクの回転が下がったきたらロー側へ1枚分変速
- これを繰り返す
- 停止する前に走り出しやすいギアに変速しておく
ポイントとなるのはクランクの回転数です!!
なるべく一定に回すのが楽に走るコツです。
平地の場合を例にすると、おそらく多用するのはトップの方から3~5枚目位ではないかと思います。
「トップギア」と「ローギア」はほとんど使用せず、下り坂でたま~に「トップギア」を、登り坂で「ローギア」を使用する程度だと思います。
「ローギア」でクランクを「回せなくなる前」に降りてしまった方が安全です!!
変速機を使い慣れてきたら、停止する前にあらかじめ漕ぎだしやすいギアに入れて置くことを意識しましょう。走り出しがスムーズになります。
- 良く?たまに?見かける走り出しと同時に、「ガチャガチャッ」と変速するのは発進がもたつく原因となります。
- 大きな力がかかる発進時に変速させるのは、変速機やチェーンに大きな負担をかけることになります。
次に変速機を使用する上での注意点を記します。
変速機やチェーンを痛めないために
変速機の操作はクランクを回している時に行う!!
止まっている時に変速レバーを操作しても当然ですが変速はできません。
前の項でも記しましたが発進時の変速操作は避けたいです。
それは大きな力が変速機やチェーンにかかってしまうからです。
最近の多段化した「ロードバイク」などでは、チェーンも細くギアの歯(スプロケット)も薄くなっているので破損することもあります。
変速する時にクランクかかっている力を一瞬抜く!!
- クランクが少し重くなったな~
- クランクの力を少し抜く(ここがポイント!!)
- 同時に変速レーバーを操作
- ギアが変速されたらクランクに力を加える
一連の流れはこんな感じです。意外に奥が深いです。
この動作ができるだけで、変速が「ガチャン」から「カチャン」に変わります。
自転車のメンテナンスの状態により効果に個人差があります。
余談ですが 変速機はディレーラーと呼ばれています
レールを外すから?ディレーラーですね。
変速動作はギアからチェーンを一度外して隣のギアへ移す動作を行います。
以上の理由から変速時の不安定な状態で、力を加えるのは避けたいのです。
またチェーンがよじれるような力のかかる、急激な変速も避けたいです。
ギア変速についてのまとめ
普段何気なく使用している変速機の操作についてしるしました。
「なるほど~」と思われた方もいると思います。(いてほしいです)
皆様には「ギア選択の自由」があります。
まずは「ガチャガチャ」変速機を操作して、少しでも自分が楽に走れるギアを選びましょう。
- 走り出しのギアを決めて1枚ずつ変速させる。
- 止まる前に走り出しのギアに戻しておく。
- 応用で変速時はクランクの力を少し抜く。
以上が要点になりますね。
この内容を知っているだけで今後の自転車との付き合い方が変わるかも知れませんね。
「だって子供の頃、変速させるの楽しかったもん!!」
ところでこの内容を知ったことで後悔してない?
それは・・・
「変速操作して使えるようになった時、後悔することになるでしょう!!」
ここまで読んで頂きありがとうございました。
楽しいサイクルライフを送りましょう。
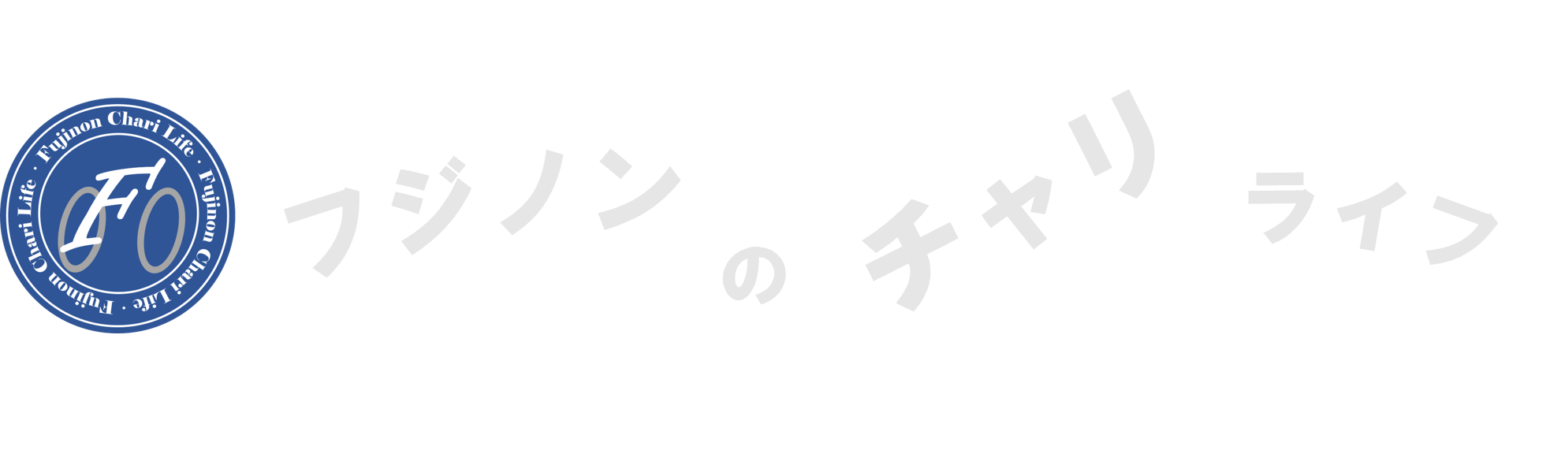



コメント