
エコブーム、健康、満員電車回避などを理由に「自転車通勤・通学」をはじめる方も多いのではないでしょうか?
しかし、はじめる方がいる一方で辞めていく方がいるのも事実です。
楽しい「自転車通勤」だったのに「いつの間にか・・・」の理由です。
私の経験上での内容です。人ぞれぞれの住環境も違いますのでその辺を加味したうえで、「自転車通勤」を続けるための参考にしてください。
- 予想以上にメンテナンスに手間がかかる(特にロードバイク)
- 会社や学校の問題(ハイブリッド通勤可能?)
- 健康上の問題(腰痛の原因は自転車通勤?)
- 走るのが怖い(歩行者その他、駆け引き?の問題)
他にも問題はありますが以上の4点をメインに進めます。
少しでも問題点を減らして楽しい自転車通勤を「開始または復活」できることを願っております。
【メンテナンス】に想定以上に手間が掛かる(特にロードバイク)
「ロードバイクは走る精密機械」と聞いたことがある方もいるかと思います。
見た目は同じ「自転車」です。
「普通の自転車のスポーツタイプ」と認識されている方もいるでしょう。実際私も「ロードレーサー」を購入当時は「スピード出る自転車」と認識してました。
「自転車」には変わりないから扱いも今まで通り「ママチャリ」と同じで・・・
と考えているようでしたら、数年で?もしかしたら数ヶ月で挫折し、「駐輪所の肥やし?」と化してしまうかも知れません。
マンションの駐輪所に哀れな「ロードバイク」が数台・・・「チェーン」や「スプロケット」は赤く錆びています。もう来ない出番を待っているようです。
こんな光景を目の当たりにすると複雑な気持ちになります。
怒らく想定していた以上に「メンテナンス」が面倒で、そのままになってしまったのではないか?
と想像してしまいます。
颯爽と走る「ロードバイク」の姿にあこがれて、購入してしまった方に多いパターンです。
「アレ」に乗れば俺は風になれる!!
と思っていたのだが、いつの間にやら「他の風」に流されてしまったのか・・・
地球環境にも配慮して、エコな乗り物の代名詞的な「自転車」を選んだのに環境破壊の片棒を担いでしまった・・・
「もの」は何でも長く使用した方が環境負荷が少ないです。
かなり「大袈裟」な言い方です。人は生きていく上である程度「環境に負荷をかける」のは仕方のない事です。
それが「目の前で起きているか」「見えないところで起きているか」の違いですので。
話を戻しますと・・・「メンテナンス」に手間がかかるのは「自転車通勤」に「ロードバイク」を選んでしまった運命です!!
もともと自転車好きで普段から自転車の「メンテナンス」をしてきた方には特に問題とならないことです。
しかし、今まで全くと言っていいほど「メンテナンス」を自転車店にお任せしてきた方にとっては、「ロードバイク」の「メンテナンス」は想像以上にハードルが高いと感じるはずです。

一番重要な「空気圧の調整」すらあまりしない方は、覚悟しておいた方がいいかも知れません。
「ロードバイク」のタイヤは「高圧タイプ」なので数日で違いを感じられるほど空気が減ります。
購入時の状態を維持するにはそれなりの知識が必要です。
タイヤの空気圧をはじめ、メンテナンスを続けることが性能を維持するために必要になります。
「ロードバイク」の「メンテナンス方法」もネットで検索すれば、とんでもない数がヒットします。
正直このブログ内にある「最重要メンテナンス」でも極々当たり前の事をわざわざ案内してます。
だけれども「それがあたり前でない方もいる」のが現実なんです。
- タイヤの空気圧が減ったら入れる
- 定期的に注油する(チェーン、ブレーキアーチ等)
- ブレーキの引きが多くなったらブレーキインナーワイヤーを締める
- 変速フィールが悪くなったらシフトワイヤーを締める
- 異音やガタが出たら確認して増し締めする
どうでもいいような内容の事ですが、できない人もいるのが現実です。
私のようなポンコツが勉強苦手なのと同じ?です。サクッと覚えて応用が利かないのとね・・・
ネットで何でも検索できる世の中です。しかし「メンテナンスブック」の1冊も読まない方は「ロードバイク」のメンテナンスが面倒になります。
やがて「ロードバイク」通勤から離れてしまうことになります。
「メンテナンスブック」を1冊は購入して手元に置いておくのをおすすめします。
何かある度にネットで検索するのも面倒だからです。
「自転車通勤」を続けるのに必要な資質は
- 「自転車が好き」である事
- 「メンテナンス自体が好き」である事
これに尽きると思います。
もちろん「メンテナンス」にはそれなりにお金もかかります。
タイヤも減りますし、走行すると喉も渇きます。ドリンク代や補給食代?がじわじわと効いてきます。
口実にそれなりの「ロードバイク」を購入し、いざ「自転車通勤」をはじめると「ガソリン代以上の飲み物代」がかかってしまうのは想定外だったりします。
飲み物は「自動車」で通勤して「缶コーヒー」でも飲めば同じですけどね。
「健康が手に入れられる」と考えられるうちは問題ないのですが、「自転車通勤が少し面倒」に感じた時にやめてしまいがちです。
会社の問題【駐輪スペースの確保】
普段が「電車・徒歩通勤」なら会社に「駐輪スペース」があるか?
工場勤務ならこの問題は特にないとは思われます。パートさんが毎日元気に「ママチャリ」で通ってますので・・・
私の「自転車」が一台増えたところで何の影響もありません。
普段の通勤が「電車と徒歩通勤」で「自転車の通勤」に切り替えるとなると「駐輪スペースを確保」の問題も考えなければなりません。
少し駐輪する位なら・・・仕事の間「1日中歩道等に置きっぱなし」とかはどうかと思います。
しかも、盗難やイタズラも心配です。社内(建物内)に持ち込めればいいのかも知れませんが、それには会社の理解も必要です。
普段が「自動車通勤」なら「駐車スペース」の確保の問題?
普段の通勤が「自動車通勤」なら「自転車通勤」に切り替えても特に問題はないかも知れません。
しかし、通勤距離が5㎞を超えてくると「自動車での通勤があたり前!!」と言ったような「暗黙のルール」があったりします。
また今度は「駐車場確保の問題」から、あまりにも「自転車」での通勤ばかりしていると「経費削減」や「他の人に割り当てるため」と言う名目で駐車スペースを確保できなくなることがあります。
「ハイブリッド通勤」が行えなくなるのは、通勤手段の選択肢が減るので何かしらの「リスク回避」が行いにくくなります。
リスクの例としては、明らかに帰宅時間が遅くなる時「午前様」でも自転車で帰宅しなければなりません。
この言い方が存在するのか定かではありませんが「電車通勤」「自動車通勤」など、複数の通勤手段を業務の状況、天候や体調などに応じて使い分ける通勤方法です。
- その日の状況に応じて、通勤手段を選べるので「自転車通勤が長続きしやすい」
- 健康的で身体からパワーがみなぎる?
- 会社の状況により駐車場スペースを確保できなくなる可能性がある
- 程よく「自動車」での通勤も行わないと「ハイブリッド通勤」しにくくなる
自動車の駐車スペースを確保できなくなると「体調が悪くても」自転車で通勤しなければなりません。
多少の体調不良でも休みをいただけるような余裕のある会社なら問題ないのですが・・・そんな会社はそうそうありません。
「ハイブリッド通勤」するためには無理をせず、適度に「自動車通勤」を挟むのが駐車スペース確保のコツです。
会社も余裕がなくなると「自転車で通勤できるのなら駐車スペースはいらないね」と言われかねません。
- 空いた駐車スペースはお客さん用に開けておきましょう。
- 他の会社に貸し出して少しでも賃料を得よう。
などと言われかねません。そして一度駐車スペースをなくしてしまうと、戻すのはなかなか難しいものです。朝どんなに早くても、逆に業務が遅れて夜中になっても「自転車」で通わなければなりません。
雨の日も風の日(かなりの強風)でも、雪の日も・・・(遅れてでも歩いていきましょう)
健康上の問題 腰痛など
頑張り過ぎて?「腰痛」とか・・・
正直私の経験では「自転車が原因で会社の業務に影響が出たことはない!!」と断言できます。
「腰痛」も業務の「長時間の事務作業」や「重い荷物を持った時」「無理な姿勢での作業」が原因であることがほとんどです。
「自転車」が原因なら会社から「自動車通勤にしろ!!」と言われるでしょうし・・・
- 仕事にとりかかるアイドリングの必要がなく、スムーズに作業に取り掛かれました。
- 頭もスッキリしていたことがほとんどです。体の疲れもそれ程負担には感じることはなく、むしろ自動車通勤の方が体力が落ちたの実感します。特に階段はきつく感じます。
「自転車通勤」に備えて規則正しい生活になっていたのも影響していると思います。
走るのが怖い 駆け引き問題?
「ロードバイク」だろうが「ママチャリ」だろうがある程度の速度で走行しているので、スピードに対しての恐怖があるわけではありません。
YouTubeの「ロードバイク」批判動画で見られるように「かっ飛ばしている」なら話は別です。
一般的な自転車と流れを合わせて走行しているのなら危険度はほぼ同じです。
私自身が周りの状況判断ができなくなったのか?
または考え過ぎで恐怖心が生まれてしまったのか?
少し振りかえってみました。
- 歩行者との駆け引き
- 自転車との駆け引き
- 自動車との駆け引き
- 自分自身の駆け引き(判断の迷い)
歩行者との駆け引き
全ての歩行者に該当することではありません。気になるのは「横断歩道も関係なく渡ってくる方」が少なからず?いやいや少数ですが存在することです。
信号待ちで停車しているクルマの間をすり抜けて人影が見えた時は「ヒヤリ」とします。
すぐ先の横断歩道を利用すればいいのに・・・結構怖いです。
その先の「横断歩道」まで行くのに数十メートル歩かなくてはならないのは「よ~くわかります」分かっているつもりです。
しかし「そこは横断するところではありませんよ~」と言う気持ちが勝ってしまい何となくイライラしてしまうことがありました。
「自転車の存在に気付いていない」ことが多いからです。「自動車」には注しても「自転車」は恐らく「歩行者」としてカテゴライズされているのでしよう。車道の左側を走行していることを忘れている方も見られました。
忘れているというより認識していないのか?
そして「おまえ何で車道走ってんだ!!」と逆ギレされたりして・・・
幸いにも「あわや接触」という事態にはなったことはありません。歩道から今まさに渡ろうとしているご年配の方を100m先に発見した時から駆け引きがはじまります。(横断歩道ではありませんよ)
正直その「歩行者との駆け引き」に疲れてしまったのも原因の一つです。
この駆け引きは「自動車」での通勤も条件は同じです。しかし「自動車」の方は「危険である」と認知されているので、渡って来ることは少ないです。(少ないだけで実際は渡る方もいます)
相手との距離感なり速度感の認知・判断に何らかの衰えがあることを「認識していない方」もいらっしゃいます。そのような方は車道の端を10キロ位で走行している自転車でも、「暴走してきた!!」と認識されるかも知れません。
相手がどう思っているかは分かりませんが「暴走してきた!!」と一方的に言われればカメラで撮影でもしていない以上証拠がありません。
「やっかいな人」との「やっかいなこと」には関わりたくありません。接触なんかしたもんなら何を言われるか分かりません。想像しただけでも面倒です。
予防策は常に頭の隅に置いておかなければなりません。
幹線道路は「横断歩道」を使用した方が安全なんですがね・・・
でも「分からない人には分からない」のが現実です。
少々しつこくなってしまいました・・・
この辺は高齢になる私の親の感覚を参考にしています。(10年前は他人にもう少しおおらかだったのに・・・)
自転車どうしの駆け引き
「自転車」どうしの駆け引き?はもっと面倒です。
- 限りなく「自動車」のカテゴリーに考えている方
- 限りなく「歩行者」のカテゴリーに考えてる方
かなり広い認識のバラツキを感じます。
「自転車」は「軽車両」です!!
しかし正直どちらでも構いません。
やっかいなのは「軽車両と歩行者のハイブリッド走行?」です。
「歩行者」として歩道を走行していると思ったらいきなり車道で「軽車両」に・・・歩道と車道を行ったり来たり。
「都合のいいところのいいとこ取り?」この気持ちは分からなくもないですが、周りの状況をしっかり判断して行わないのは怖い存在です。
歩道には歩道の流れがあり、車道にはその流れがあります。
流れを乱すのは大変危険な行為です!!
歩道で人が歩いていると車道へひょっこり出てきて、車道が詰まってくると歩道に戻る・・・
走り方の想定はしておりますが、後ろも確認しないで出てくるのはないよね~。
余談ですが車道を走るランナーは気持ちは分からなくもないですが・・・微妙です。
自転車からすると「道路の石ころ」のような存在です。
広い道路ならあまり気になりません。しかし狭いところだと妙に気になります。
たまに見かける「命知らずの逆走ランナー」は論外ですね。
自動車との駆け引き
自動車との駆け引きも結構疲れます。当然ですが朝は特に急いでいる方も多いです。幹線道路を走行していると路地から「出るのか?出ないのか?」の判断に迷っている様子です。
感覚的に「7割8割は無理して出る」と判断しています。路地からの「自動車」が見えた時には減速して対応しています。
しかし「このタイミングででてくるか?」という「マイペースな方」もいるので注意が必要です。
予想するに、そのドライバーは「自転車は歩行者にカテゴライズ」されているのでしょう。速度感覚を見誤ってます。
この辺のドライバーはまだ可愛いものです。
本当に怖いのは「一時停止線を振り切って道路の淵まで出てくる自動車!!」です。
「一時不停止です!!」
ドライバーからすれば「停止線超えても止まっているから問題ないでしょ?」と言う理屈でしょうが、そこに停止線がある意味を想像した方がいいです。
歩道を勢いよく走る自転車を引っ掛けるのはこのパターンです。こういう現場を通勤途中で何度も見かけると「次は我が身?」と想像してしまうのは考えすぎでしょうか?
「一時停止」では止まるのが規則ですが、そこはもはや「チキンレース」です。
こちらは減速して対応しますが、先方はすかさず止まるや否や優先道路に出てきます。これは最悪なパターンです。
優先道路に自動車の鼻先を「ツライチ」で止められても、その前をすり抜けるのは怖いですね。
自分自身の駆け引き(判断の迷い)
自らを棚に上げて記してきましたが培われた「走行感覚は」他人は変えられないものです。
自分自身でどのようにすべきか判断しなければなりません。
「自転車通勤」し続ければそれらの問題に対応できるのでしょう。
しかし離れると離れただけ「走行感覚」問題は大きくなっていきます。
判断能力の低下も考えられますが、過信するよりは安全であると思います。
判断に余裕を持たせるために、通勤時間には十分な時間的な余裕をもって無理せず行いたいものです。
ゆったり走行しても5㎞位ならそれ程時間の差はなく、信号待ち数回の誤差程度です。
調子がいい時悪い時あるものです。その時に応じて緩急入れて通勤するのも楽しいものです。
極力他社との駆け引きを避けて「安全第一、速さは第二・・・」で張り合わずに、譲り合いの精神で走行することをおすすめします。
実際は「アドレナリン」のせいで理論通りには行かないかもしれませんが・・・
番外編「自転車通勤」の最大のデメリット?
音楽などを聴きながら通勤できない
音楽だけでなく、YouTube動画の視聴をしながらの通勤ができないのは「最大のデメリット」かも知れません。
※YouTube動画の視聴に付きましては画面を見るわけではなく「聞き流しているだけ」ですので念のため。
通勤時間30分 行きと帰りで1時間程です。月間で20時間は確保できます。
年間通すと結構な時間です。
昨今の感染症の問題で会社の状況はあまり良いとは言えません。精神的なことかも知れませんが何となく「自転車通勤で楽しく」と考えられなくなってしまいました。
気持の焦りから「会社でも少しでも役に立てるように」また「何か不測の事態が起こった時に対応できる」ようにしなければと無能ながらに思うものです。
自由時間も増えたことから「読書量は増え」ました。それはいいことですが一方で「社会との疎外感」も感じている状態です。
移動時間も少しでも何かしらの「インプット」をしておきたいと「本の要約チャンネル」なんかを聞き流すようになってしまいました。
「自転車通勤」ではコレは無理ですよね。イヤホンしている方も見かけますが危険ですし「そこまでするか?」とも思います。
【ロードバイク】通勤をやめてしまった理由 まとめ
エコブームで「自転車通勤」をはじめる方も多いと思いますが、一方でやめていく方がいるのも現実です。今回は「自転車通勤」から離れていく理由をいくつかあげてみました。
- 予想以上に手間がかかる(特にロードバイクのメンテナンス)
- 会社の問題(ハイブリッド通勤可能?)
- 健康上の問題(腰痛の原因は自転車通勤?)
- 走るのが怖い(歩行者その他、駆け引き問題)
- 番外編 最大のデメリット「音楽などを聴きながら通勤できない」
「ロードバイク」のメンテナンスは想像以上に手間がかかります。「ママチャリ」とは違い空気の減りも速いです。
性能を維持するためにはメンテナンスが必至です。
今まで自動車通勤だったのなら、自転車との「ハイブリッド通勤」がおすすめです。
適度に使い分けることによって、自動車の駐車スペースも確保でき「自転車通勤」が長続きする可能性が高くなります。
健康上の問題は「特に頑張りすぎなければ」問題になることは少ないと思います。「自転車通勤」が原因で体調不良になるようなら、「自動車通勤」との「ハイブリッド通勤」で対応しましょう。
走るのが怖い問題は慣れの問題かもしれません。しかし通勤中にケガをするようなことがあれば会社としては労災になるので「自転車通勤禁止!!」になってしまう可能性もあります。
こればかりは「充分注意して」と言うしかありません。
可能な限り「譲り合いの精神」で走行してください。
後は番外編の説明ですが生活の安定があっての「自転車通勤」です。(特に趣味のロードバイク通勤の場合)
学生の頃やまだ若いうちならどうにでもなるかも知れません。ならないかも知れないけど・・・
歳をとると現実逃避もなかなかできないものです。
心の底から楽しんで「自転車」に乗れるようになりたいと願っています。
(普通には楽しいけど楽しめていないので・・・)
以上になります。安全な走行のために、自転車通勤を長続きさせるために参考にしていただければと思います。
楽しいサイクルライフをすごしてください。
よろしければこちらも参考にしてください。
【ロードバイク】通勤・通学をはじめる時の記事です。
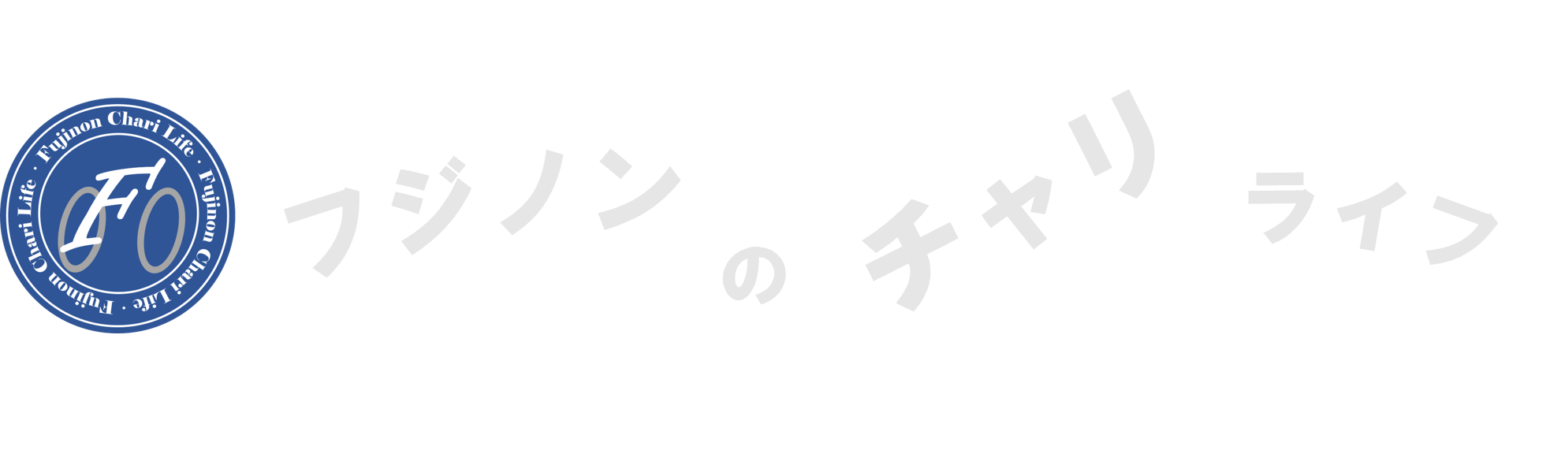




コメント