
「自転車」の整備には「ネジ」や「ボルト」を締めたり緩めたりがつきものです。「自転車」に限らず日常生活のあるとあらゆる場面で使用されている部品です。
最近我が社(食品工場)にめでたく新入社員が入社してきました。コロナの影響もあり数年ぶりの事です。
20代前半の女性です。
分解作業を行う時に「ネジの回す方向が分からない」という事がありましたので、ここで改めて記して参りたいと思います。
「ネジ」のピッチがどうのこうの難しい事ではなく「ドライバー」や「スパナ」の使い方程度の内容です。
でも改めて説明しようとすると知ってそうで知らないものです。
右に回して緩まないのなら左に回せば良いだけの事です。
しかし、締まる方向に力を加えてしまい、「ネジ」が硬く締まって外せなくなったり、時には「ネジ」を舐めてしまったりしたらとても面倒な事になります。
知っていればそんな事はせずに「締めるのなら右回り」「緩めるのなら左回り」に回すだけですが・・・
改めて考えると結構細かい内容になってしまいました。
ところでところで「右回りって?」
「ドライバー」の使い方
「ネジ」の頭に合ったサイズの「ドライバー」を用意して柄の部分を握って回すだけです。
それだけの事なんですがあまり使用してこなかった方にはそれが通じなかったりします。
ここでは使用頻度の高い「プラスドライバー」を例に説明して参ります。
「ネジ」どっちに回す?
- 右に回す・・・締まる!!(時計の針の動き)
- 左に回す・・・緩む!!(時計の針の反対の動き)
ここでは特別な「逆ネジ」などは考えずにシンプルに記します。
回し方
「押し付けながら回す」のが基本です。基本ではないですね「鉄則」です。
プラスドライバーを使用する事が多いですが、慣れないとネジを舐めてしまう事が多いです。
感覚的に押す力が7で回す力が3位が目安です。
押す力が7・・・「こんなに?」と思うかも知れませんが、そもそも押しながら使用する事を知らない方もおります。
「ネジ」が硬い時は更に押す力が必要です。
押す力が9・・・とか。
「ネジ」を舐めさせない事が重要です。たかがネジ回しと「ナメたら開かんのです!!」
特に電動ドライバーには注意!!
「電動ドライバー」は大変便利ですが、しっかり押さえ付けないとネジを舐めてしまいます。
しかもドライバーの先がネジの溝から外れて、材料にキズを付けてしまったりケガにもなりかねません。
ネジの締め過ぎにも注意が必要です。
慣れないうちはスイッチをちょんちょんと少しずつ締める事をおすすめします。
材料が柔らかい場合は締め過ぎた末に、空回りしてネジが効かなくなる事もあります。
ご利用は計画的に!!
ドライバーの向き(角度)
当然ですが「ネジ」に対してまっすぐに押し込みます。
斜めに回すと力が分散してしまい「ネジ」を舐めやすくなります。
子供のおもちゃで電池を交換しようとすると結構な割合(肌感覚で9割)は舐めて締まっている感覚です。
子供が親の真似をしてドライバーを使用してネジ山をぐりぐりしてしまうのが原因ですね。
これも教育の一つですので、「ネジ」の回し方を覚えるためにも必要な行為です。
私も小さい頃(小学生に上がる前)から電池の交換をしておりましたので、何度も失敗して覚えていくものだと思っております。
何度も失敗して押し付けて回す事を覚えました。実際は父親に聞いたり、どうしても硬くて緩まない時にはお願いしたりもしました。
時にはネジを舐めてしまいどうにもできなくなって泣きついた事も・・・
遊びたいのに動かせない。
このような子供ながらに苦い経験をして、少しづつ大人になるのかな~
まっ、50になっても子供の様な私が言うのもなんですがね。まだ30年は生きる見込みです。
締める強さ
これは経験で覚えて行くしかないのかも知れません。子供のおもちゃ程度なら緩まなければ良いのでしょうが、自転車の調整では緩むと、異音の発生や動作に不具合が発生する事になります。最悪ネジをどこかに落としてしまう事にもなります。
気が付いたらネジが無い!!
締めるものにもよりますが、素材が傷まない程度に締まるの良いのかな?と思います。金属なら締めた時に最後に少し手ごたえがある程度かと。
あっ、少し訂正です。上に記入した「子供のおもちゃ」のネジは緩んだら大変です。部品を飲み込んでしまう危険があるからです。遊ばせる前には確認して緩んでいたり破損していたりした場合は早急に対処するべきです。
小さい子供は何でも咥えてしまいますので・・・
テレビや照明のリモコンも美味しそうに咥えたりします。丁度いい大きさなのでしょう。
しつこいですがここではトルクスレンチを使用して・・・とかではなく一般的な対処方法です。
緩まないネジは舐めないように注意!!
締める時にはネジを舐める事は少ないと思いますが、緩める時は特に注意が必要です。
締める時はドライバーを押し付けて回すのですが、緩める時は押し付けが弱くなってしまう事が多いからです。
「自転車」もそうですが「電気製品」を分解する時、結構固く締められている事が多いのも原因です。
「自転車」の場合は緩んでしまうと初期不良として重大な事になるので特に新しく購入した時には「ガチガチ」に締められている傾向があります。
新車の「自転車」をバラして調整するような「もの好き」はあまりいないでしょうし、そもそも「自転車」の場合はドライバーではなく「スパナ」を使用してますね。
例えが悪かったです。
ところで「ネジ」を舐めるとは?
「プラスドライバー」で言うとドライバーの先端が「ズリッ」と滑ってしまい、ドライバーの力を「ネジ」に加えられなくなってしまった状態です。
「ボルト」と「ナット」
少し大きなものを締めたり強く締める必要がある場合は「ボルト」や「ナット」が使用されます。
「ボルト」とは頭が六角形で外側にギザギザがある「雄ネジ」の事です。
その受け側で内側にギザギザがあるのが「雌ネジ」の「ナット」です。
分かりずらいですかね。中学校の技術の授業で習いました。
そのうち写真を用意しましょうね。
「ボルト」もネジの一種ですので回す方向は右回りで締まります。(例外の逆ネジは置いておきます)
締める時に使用する工具
「スパナ」「レンチ」は同じ意味で扱われる事が多いです。厳密には違うのかも知れませんが、その時の気分で「スパナ持ってきて!!」と言ったり「レンチどこ?」と言ったりしてますね。
「レンチどこ?」・・・工具の場所を探すのはよくないですね。いつも決まった場所に置いておかないと作業効率は悪くなりますね。
「テレビのリモコンどこ?」「スマホどこだっけ・・・」また脱線。
「スパナ」

一般的には片方が開いている(U字型)のものは「スパナ」、閉じているものは「レンチ」なのでしょう。「メガネレンチ」と言いますけど「メガネスパナ?」とは言いません。
写真は「自転車」のハブ調整に使用する「薄口スパナ」です。「ハブスパナ」と言われたりもします。
「レンチ」
「メガネレンチ」は六角のボルトにはめて使用します。締めている時にずれないのでボルトを舐めてしまう心配が少ないです。
狭いところで何度もボルトを回すときは「スパナ」の方が扱いやすく、力が必要な最後に「メガネレンチ」で固定するのが一般的な使い方です。
ラチェット機能のある「メガネレンチ」なら「ボルト」にはめたままカチカチと締められるので便利です。
「ラチェットレンチ」と言います。
「モンキーレンチ」
「ボルト」のサイズに合わせて幅を自由に変えられる便利なレンチです。
一般家庭で適当なサイズのものを2本持っていれば大抵の「ボルト」には対応できるのではないでしょうか?
「自転車」をメンテナンスする時にも便利です。【ママチャリ】メンテナンスに必要な 超・超基本工具3選でも詳しく記してあります。
「モンキーレンチ」の欠点

こんな万能な「モンキーレンチ」ですが重大な欠点があります。
それはボルトに負担がかかりやすい事です。しっかり「ボルト」に合わせていても締めている間に少しづつ隙間ができたりします。
その隙間が一定以上緩むと「ズリッ」となる訳ですよ。そう、「ボルト」を舐めてしまうのです。
誰もが経験するであろう重大な欠点です。
また、「スパナ」や「メガネレンチ」に比べて頭が大きくなります。この頭の大きさが災いして「ボルト」をしっかりつかめないなんて事も結構あるあるです。
当然ですが狭い所での作業は苦手です。スパナより重いし・・・
「ネジ」「ボルト」「ナット」について まとめ
食品工場での出来事から改めて記事にしてみたのですが、正直なところ記事にするのが難しい。
普段何気なく使用しているし考えてもいなかった内容です。
今の世の中「スマホ」を持っていれば何でも検索可能ですが、「ネジ」の回す方向まで調べないといけないのか?
締め付ける力加減も・・・と考えると「そこまでやるか?」となりますね。
この記事で簡単ですが「ネジ」の回す方向と締め加減、「ボルト」「ナット」とそれらを締めるために使用する工具「ドライバー」「スパナ」「レンチ」について簡単に分かったのではないでしょうか?
このサイトは「自転車」「ママチャリ」で快適な生活を目指しています。
少しのメンテナンスで自転車の寿命が延びしかも快適に使用できます。
これを機会に「ネジ」や「ボルト」が緩んでないか「チョット見てみようかな?」
となっていただければ幸いです。
あっ、空気圧の確認も忘れずに!!
空気圧の確認については【ママチャリ】空気入ってますか?「空気圧の管理」は自転車メンテの基本でも触れています。よろしければ覗いてください。
では快適な自転車ライフを送ってください。
ありがとうございました。
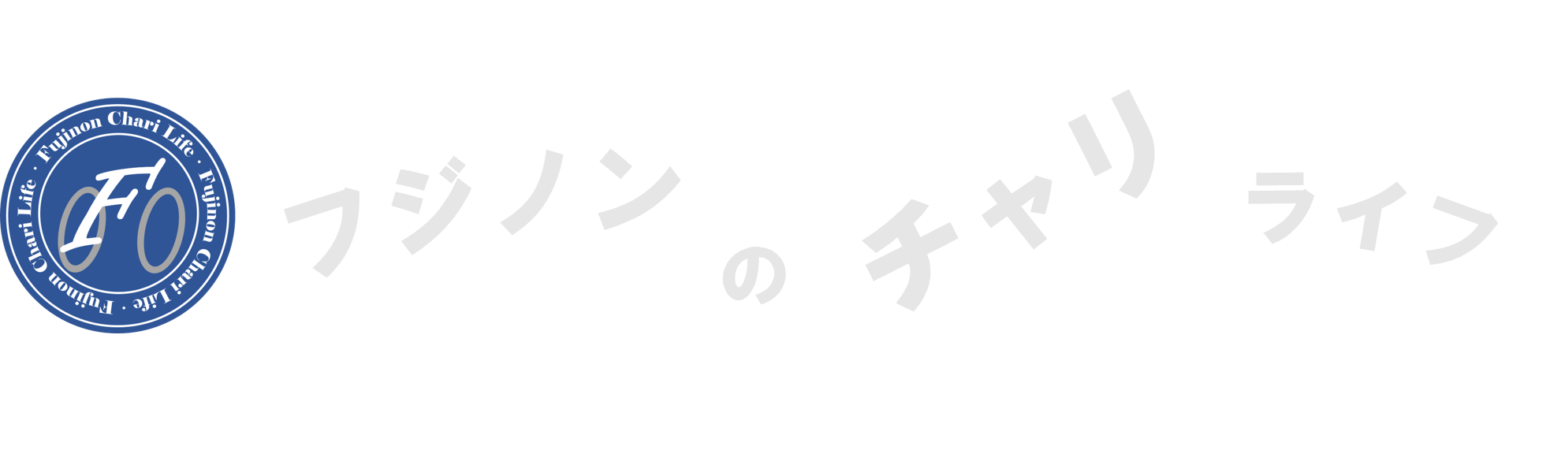



コメント